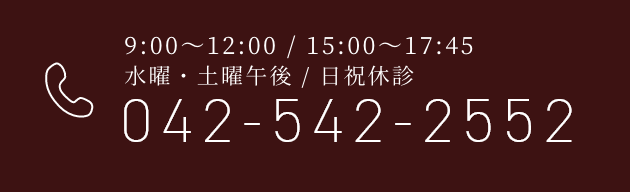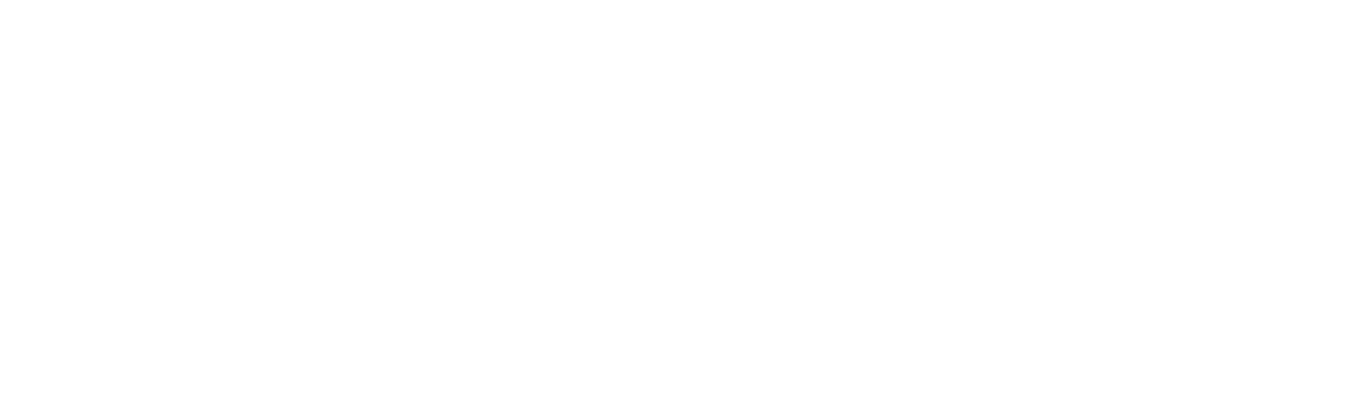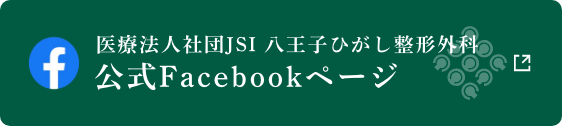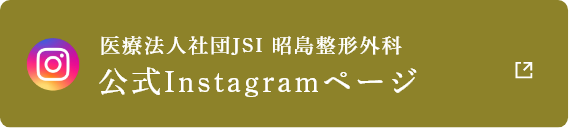機能解剖学に基づく治療
当院では機能解剖学をベースにした理学療法を実施しています。
機能解剖学とは…筋、骨、関節、靭帯、(末梢神経も含む)の働きに着目し、四肢や体幹の身体機能との関連を研究する解剖学領域のことです。
当院では機能解剖学に基づいた治療コンセプトをもとに技術の向上と発展に日夜努力しています。
入職後は当院独自の教育システムを採用
3年間で1人前の理学療法士になるよう、臨床現場でよく目にする12疾患を段階的に教育するシステムや機能解剖学的な触診技術の習得を行っています。
1年目は12疾患を一通り学び、基本的な病態を学びます。1疾患ずつ学び終えた後に筆記・実技テストがあり、患者さんへの介入を行う前に技術が定着しているか確認を行います。
2年目以降はより実践的な技術習得に向け触診テストを行います。
肩・肘・腰・股・膝・足に分けて一通り触診をできるように学んでいきます。
3年目以降は新人講義のアシスタントを行い、学ぶ立場から教える立場になることでより知識を深めていきます。
主な12疾患
- 変形性膝関節症
- 腰痛症
- TKA・UKA・HTO
- 拘縮肩・肩関節周囲炎・腱板断裂
- THA
- アキレス腱症・足底腱膜炎
- ジャンパー膝
- 足関節捻挫(テーピングを含む)
- 膝前十字靭帯損傷
- 外側上顆炎・内側上顆炎
- 変形性股関節症
- 投球障害(野球肩・野球肘)
- 変形性膝関節症
- TKA・UKA・HTO
- THA
- ジャンパー膝
- 膝前十字靭帯損傷
- 変形性股関節症
- 腰痛症
- 拘縮肩・肩関節周囲炎・腱板断裂
- アキレス腱症・足底腱膜炎
- 足関節捻挫(テーピングを含む)
- 外側上顆炎・内側上顆炎
- 投球障害(野球肩・野球肘)
勉強会の風景


講義を受けた感想
- 初めての介入は緊張しましたが講義を受けたおかげで自信をもって患者さんに治療や説明が行なえました!
- 講義を受けることで機能解剖学に基づいてどう治療すべきかを考えることができるようになりました!
- 機能解剖学に基づいた講義を受けたおかげで病態の理解を含め、自分のスキルアップに繋がりました!
- 講義を指導する側になることで知識の整理ができました。
- 触診の練習を通して触診技術が向上することで、治療の質が向上し患者さんに褒めてもらえることも増えました!
- 新人への講義など指導する立場につくことでより一層知識を深めることができました。
- 機能解剖学に沿って一から学べることで基礎知識がつくことはもちろん、臨床にも活用することができます。